【うつを経験した教員】自分を大切にする「記録する手帳術」

教員専門ライフコーチの蒼井櫻子です。
実は私自身、教員3年目にうつ病を発症し、闘病した経験が約6年間あります。そんな苦しい時期を支え、自分を大切にする生き方を教えてくれたのが「手帳」でした。
今日は、私がうつの闘病中に実践してきた「記録する手帳術」についてお話しします。
これは、単なるスケジュール管理ではありません。自分の心と体を守り、自分軸でしなやかに働くための具体的な方法です。
※ SpotifyやAmazon MusicなどのPodcastアプリでもお聴きになれます。
「蒼井櫻子」または「先生だって定時に帰ります」で検索🔍
私が手帳を使い始めた理由-うつ病との闘い-
私が本格的に手帳と向き合い始めたのは、教員3年目にうつ病と診断されてからです。
そこから5年間の闘病、そして一度「寛解」した後の再発…。合計6年という長い時間、私は心療内科に通いました。下の写真は発症から1年半が経過したころ。拒食でガリガリに痩せていたころです。治療開始直後は、過食でパンパンになりました。

うつ病は「完治」するのではなく、症状が落ち着いている「寛解」という状態になります。だからこそ、うつが再発しないように、そしてもし不調の波が来てもうまく付き合えるように、自分自身を客観的に観察する必要がありました。
そのための最高のツールが「手帳」だったのです。
当初は、主治医と話すために記録を付け始めただけでした。
受診のたびに心身の状態について報告する必要があったのです。診察室にいる瞬間の感覚ではなく、長期的な記録をもとに間違いない情報を伝えて治療したいと思いました。
【実践編】心を整える「記録する手帳術」
闘病生活の中で私が手帳に書き続けたのは、主に2つです。この2つの記録が、自分を客観視し、心を守るための土台となりました。
ポイント①:睡眠時間と日々の「体と心」を記録する
うつの患者にとって、睡眠時間の確保は「死活問題」なので、日々の就寝・起床時間を記録していきました。
けれど、睡眠時間の確保は精神疾患をもっていなくても、心身の健康の土台ですよね。
【具体的な記録内容】
①就寝・起床時間の記録
そもそも床に就く、起きる時間は目標時刻を決めておきます。手帳には黒で書いておきます。
そして実際の就寝・起床時間を赤で記録しておきます。寝る直前や、職場で手帳を開いた時に書き込んでおくといいと思います。
②日記
ここで書くのは、その日の出来事ではありません。自分の「内側」で起こったことです。
体調・反応:体の感覚
「体が重い」「頭が痛い」「めまいがする」
心が動いたときに起こる体の反応例)傷ついた時に感じる胸の痛み
感情・思考:心の動きや考え方の癖
「イライラした」「悲しかった」「漠然と不安だ」
「べき・ねばで行動した気がする」「考えの違う人に期待している」
これを手帳の隅にある小さなスペースでいいので、毎日記録していきます(写真参照)。
数日間、「頭が痛い」という記録が続けば、「今、自分は疲れているんだな」と客観的に認識できます。これが「不調のアラート」となり、「近いうちに有給を取ろう」「今日の午後は無理をしないようにしよう」といった具体的な対策を打つきっかけになるのです。
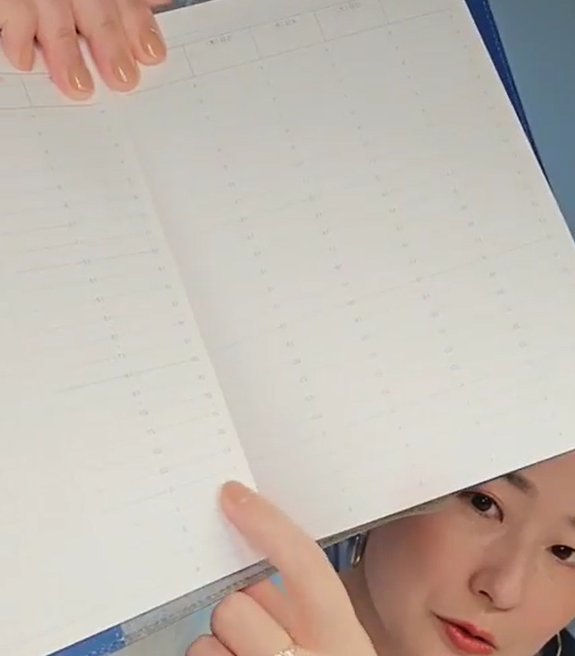
ポイント②:タスクと時間を「見える化」し、仕事量をコントロールする
心身が疲れている時、どうしても仕事の処理速度は落ちます。その結果、残業時間が増え、さらに疲弊するという悪循環に陥りがちです。
そこで重要になるのが、「タスク自体を減らす」という考え方です。
【具体的な実践方法】
①タスクにランク付けをする
まず、すべてのタスクを重要度A~Cに分類します。ごく簡単に書くと、このようになります。
A:組織が回るために必要なこと
B:自分にとって便利なこと
C:誰か特定の人を喜ばせたくてやること
詳しくは、無料プレゼント【確実に仕事を減らすやることリスト】で解説していますので、仕事の優先順位に迷いたくない先生はこちらからダウンロードしてみてください。
ランク付けができたら、Cランクのタスクはやらないと決めます。
驚くかもしれませんが、私たちが「子どもたち・生徒たちのために」と思ってやっている仕事の中には、自己満足に過ぎなかったり、過保護になっていたりするものも少なくありません。そういった仕事は思い切って手放してみるんです。
正直、初めはとても怖いはずです。罪悪感さえ抱くと思います。でも、このチャレンジで「この仕事は本当に必要なのか?生徒や若手の成長の機会を奪っていないか?」とものごとの本質について考える時間が増えます。
それが、あなたの自分軸に変わっていくんですね。
そして、どうしてもCのタスクを手放すことができないとき、あなたに語りかけてきた心の声が「働きすぎる思考」の正体だとわかります。
②仕事にかかる時間を記録する
各タスクにかかった時間を記録していくと、「この作業には平均〇分かかる」という自分だけのデータが蓄積されます。これにより、無理のない計画が立てられるようになります。
これを続けることで、「先生だから何でもできなきゃいけない」という思い込みから解放され、自分の得意なことで組織に貢献するという、より健康的で生産的な働き方にシフトできます。
写真は、寛解の直前のもの。この年の夏休みに初の渡英(2週間の超短期留学)をしています。

手帳が教えてくれた、自分を大切にする生き方
手帳に記録を続けることで、私は2つの大きなものを手に入れました。
① 手帳は「心のアラート」
手帳は、自分でも気づかないうちに溜まっている疲労や、キャパオーバーを客観的な「記録」として見せてくれます。アラートが鳴ったら、それは自分を休ませるサインです。
完璧主義を手放す勇気を持つ(仕事の完成度を6割にしてみる)
無理な依頼は断る
周りを気にせず休む(実際に気になっているのは特定の誰かの目ではありませんか?)
最初は勇気がいるかもしれません。しかし、自分を守れるのは、最終的には自分だけです。
② 手帳が「自分軸」をくれる
記録を通して自分の感情の動きや思考の癖を分析していくと、「自分が本当に大切にしたい価値観」や「譲れないこと」が見えてきます。これが自分軸です。
自分軸が定まると、苦手なことや不得意なことを無理にやろうとしない
どうしても合わない人と、心身をすり減らしてまで付き合わない
他人の評価に一喜一憂せず、ありのままの自分を受け入れる
といったことができるようになります。
手帳は、どんな自分も否定せず、ただただ記録を受け止めてくれます。
そうして自分と対話し続けるうちに、他人にどう思われるかではなく、自分がどうありたいかを基準に行動できるようになるのです。
まとめ
たかが手帳、されど手帳。
ただの紙の集合体ですが、使い方次第で、自分を深く理解し、心を守るための最強の相棒になってくれます。
もし今、働き方に悩んでいたり、心が疲れていると感じていたりするなら、ぜひ今日から手帳に小さな記録をつけてみてください。
きっとその記録が、あなたらしい生き方を見つけるための、確かな道しるべになるはずです。
>>>前の記事
<<<次の記事