【手帳迷子卒業】手書きとデジタルの「役割分担」。

手帳・情報が増えるほど「迷子」になる先生へ
教員専門ライフコーチの蒼井櫻子です。
先生方からいただくお悩みで特に多いのが、「手帳もノートも冊数が多くなり、結局何がどこにあるかわからない…」という迷子の状態です。
何でも手書きで管理しようとするとジャグリング状態で情報を探せなくなるし、手帳一冊に詰め込むと、情報が氾濫し、本当に大事なことを見失いがちですよね。
今日は、その冊数や一冊当たりの情報を減らし、心に余裕を生む方法として、「手書きとデジタルの役割分担」についてお伝えします。
手帳を複数持ちしている先生や手帳で管理する情報に悩む先生、必見です。
この記事を…
※ SpotifyやAmazon MusicなどのPodcastアプリでもお聴きになれます。「蒼井櫻子」または「先生だって定時に帰ります」で検索🔍
「手帳迷子」が生まれる3つの原因
なぜ、私たちは手帳を使いこなせず、自己満足で終わってしまうのでしょうか?主な原因は以下の3つです。
1. 情報の氾濫とローテク信仰
何でもかんでも手帳に詰め込みすぎると、情報が氾濫します。
特に「手書きが一番」というローテク信仰に囚われると、量が多いほど時間がかかり、バックアップもないという非効率に陥ります。
2. 「書いているだけ」の自己満足
情報が整理されないまま「書いている」だけでは、ただの自己満足で終わってしまいます。
本当に大事なものが見えず、最終的に自分の記憶に頼るストレスフルな状態に戻ってしまいます。
3. 手帳の「役割」の曖昧さ
手帳で何を管理したいのか、その目的(役割)が本人に自覚がないため、結局どの手帳も中途半端になり、何も管理できない状態になってしまうのです。

あなたの頭を空っぽにする「役割分担」ルール
手帳迷子を卒業し、心に余裕を持つための鍵は、「手書きとデジタルの役割を明確に分ける」ことです。
今回は、私が教員時代に実践していた、効率的な役割分担を紹介します。
ご自身のケースと照らし合わせてみて、使えそうなものやヒントになるものがあれば活用してみてください。
1. データ(デジタル)管理に任せたもの
【目的:量が多いもの、バックアップ、探しやすい情報】
生徒の記録: 個人面談の気づき、平素の様子など、量が多い情報はパスワード付きのExcelで管理。バックアップも容易で、時間のある時に見直しました。
授業プリントと予習データ: Wordで生徒用と教員用を作成し、板書や解説を全てデータ化。追加の調べものも授業後にはデータに打ち込み、バックアップしました。バックアップの方法は、職場のNASに保存&自分宛にメールの2つです。
会議のメモ: PDF資料に疑問やメモを直接書き込み、紙の処分や探す手間をなくしました。
生徒の出願予定: 学校支給PCのカレンダーアプリで、入試日や出願期間を管理しました。出願書類の作成だけは手帳で管理しました。
2. 手書き管理に残したもの
【目的:自分に直接付随するタスク、備忘録、感情が絡む瞬間の情報】
担任用手帳(備忘録): ST連絡事項や生徒からの依頼など、いつ何を伝えたかの記録と、言い忘れ防止のための将来の伝言メモ。担任として自分のクラスに行くときは、持ち歩きます。
マークスのEDiT1日1ページ(B6変型)を使用。スケジュール帳であることの利点は、将来連絡することを書いておけることです。
面談シート: 生徒が事前に記入してもってくるので、そこに手書きで情報を足します。
その場でしか得られない情報や生徒向けのメモなど、一対一の生きたやり取りは手書きで行い、後にコピーをファイリング。継続的な指導や保護者とのやり取りに役立ちます。
個人タスク管理手帳(CITTA手帳): 職場で持ち歩きはせず、職員室の机上に待機。推薦書作成、志望理由書・小論文添削、教材・資料作りなど、自分自身のタスクだけを管理。他人の予定は混ぜません。
結論: 手書きは「自分に直接関係するタスクや備忘録」に絞り、量が多く、後々検索が必要な情報は「データ」に任せるのが私の最善策でした。
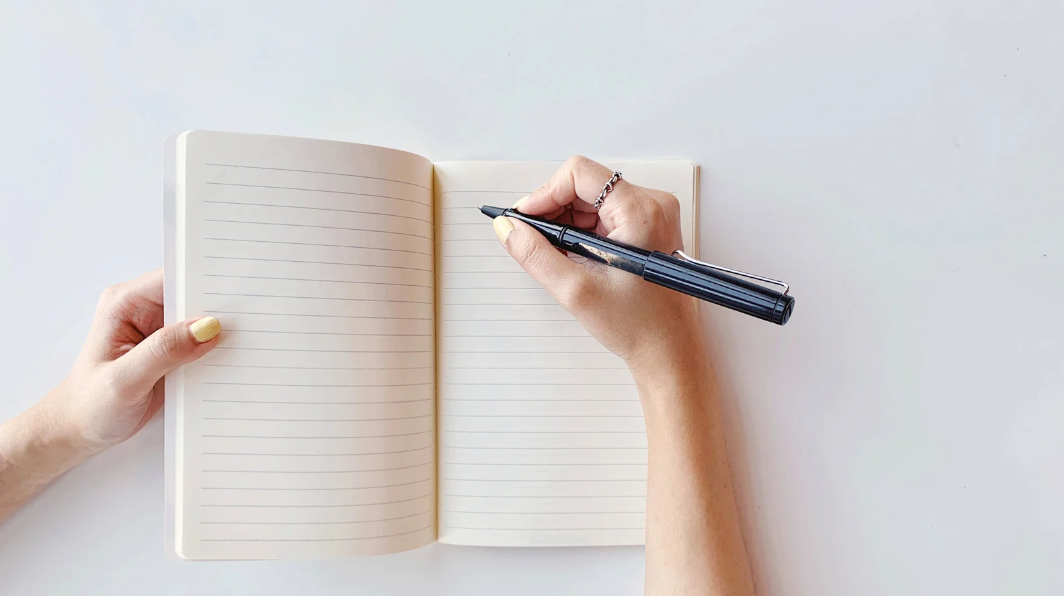
手帳迷子を卒業する2つのアクション
手帳迷子から脱出し、心に余裕を持つための第一歩は、以下の2点です。
1. 手帳に「役割」を自覚させる
まず、今持っている手帳やノートに、それぞれ「何を書き、何を書かないか」という役割を割り当ててください。
手帳は「リマインド」と「ログ」のどちらがメインか?
このノートは「思考整理」専用か、「todo」専用か?
目的を絞ることで、手帳を開くたびに「何から手をつけるか」迷うエネルギーをなくします。
2. 「ローテクにこだわる勇気」を捨てる
すべてを手書きで管理しようとせず、データ管理が得意なものはすぐにPCに任せる勇気を持ちましょう。
手帳は、あなたの頭を空っぽにしてくれる自分だけの備忘録として機能させましょう。
何でもかんでも手帳に詰め込まず、本当に大事な情報だけを管理することが、多忙な先生が時間と心に余裕を持つ秘訣です。
自分らしい「手帳ルール」を確立しよう
手帳の冊数を減らし、心に余裕を持つ鍵は、「役割の明確化」と「データとの適切な分担」です。
もし「自分の場合はどう分ければいいかわからない」「手帳の使い方が定まらない」と感じたら、ご相談にいらしてください。
あなたの課題に合わせた最適な手帳活用法を一緒に見つけましょう。
>>>前の記事
<<<次の記事