納得しながらスピードと精度を上げる。先生のためのノート術。
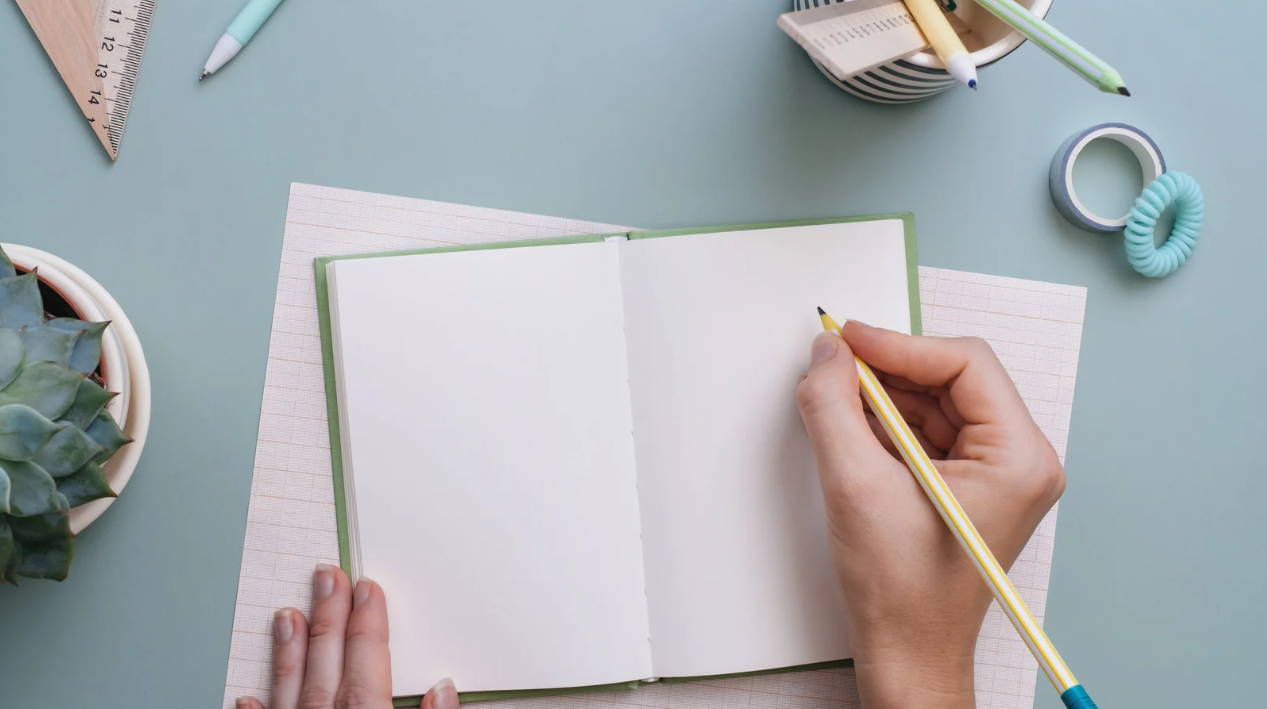
教員専門ライフコーチ 蒼井櫻子です。
前回、付箋の活用法について紹介しましたね。今日はノートのお話です。
私は、発達段階によってノートの指導は必要だと思っている人間です。
思考整理をするのにノートは大変役立ちます。頭の中だけで考えている人はまずいないですよね。
学生のうちにノートを書きなれていれば、社会人になってから「どうやって情報を整理したらいいのかわからない」状態は発生しにくいと思います。
時々、私は「守破離」の話をクライアントさんにします。
守…教えを守って基本を身につける
破…応用・自分なりの工夫で基本を破る
離…自分らしさを発揮する
小中学生のときは守。高校生は破。そこから先は離。型を身につけたら、あとは試しながら自分の型をつくればよいだけです。考える型を考えるということですね。
そういう考えがあって、中学生の指導にはノートをよく使いましたし、点検もしました。型を教えるためです。
高校生の場合は、基本的に情報量が多いのでプリントを多用しましたが、科目の特性によってノートと資料・図説で1年間やり切ったこともあります。
これについては、プリントのレイアウトや設問にこだわらなくなるので、授業準備が早く済んだ点がよかったと思っています
(とはいえ、高校生はプリントメインだったのでメモの習慣定着に力を入れていました)。
とはいえ、ここまではタブレットが導入される以前のお話。現在、あなたはどうしているでしょうか?

ノートの書き方は、ごく普通に習ってきた。
話は戻りますが…
私の場合、大体のレイアウトや使い方は学校や予備校で教わりましたし、楽な書き方は何かな?と考えながら自分の型をつくっていきました。
方眼ノートを好んで使うのにも、自分なりの試行錯誤の歴史があります。
だからクライアントさんや受講生さんに「どうやって書くの?」と聞かれても、場合によって書き分け・使い分けをするので説明に困るというのが正直なところではあります(;^_^A
方眼ノートの使い方を紹介している本がありますので、リンクを貼っておきますね。
髙橋政史『頭がいい人はなぜ、方眼ノートを使うのか?』かんき出版(2014)
👉紙書籍版
今回の記事では、「書き方」ではなく、ノートの役割に注目して2点まとめたいと思います。
A5ノートは、ハードディスク。
ノートは2冊で十分です。実のところ、1冊でも構いません。教科や用途で分けなくていいと思っています。
(教え子のなかにも自習用1冊でまとめる生徒がいましたが、数学はノート提出があったそうで、それだけは別に用意していました。)
メインは、A5サイズの方眼ノートです。見開きでA4サイズにして使用します。
※ 方眼は5mmが多いですが、私のおすすめは4mm方眼です。日本語はこちらが書きやすいですが、品数は少ないです。
これは手帳に挟むサブノートで、オンでもオフでも持ち歩いています。
会議中に考えたこと、提案内容、出張先の講演内容のメモ、仕事だけでなく引越し先のデータ、留学先の情報比較、5年間の未来予想図などなど…何でも頭の中にあるものを書き溜めておくノートです。
これは情報収集、情報整理のためのノートです。
全ページに番号を振り、1ページ目には目次を作っておきます。これはバレットジャーナルから着想を得てやるようになったことです。
このノート術で、私は「覚えるのを止める」ことができたと思っています。忘れることへの恐怖や抵抗がほとんどなくなりました。
「調べればわかることは覚えなくていい」
これは大学の恩師がよく言っていたことで、社会人になって余計に身に染みて感じるんですよね。
テストを受けるわけでもないのに、覚えてなくていいわけです。私の場合、何度も教えていることや感情が動いたことは覚えているのですが、事務的なことやアイディアはかなりの頻度で詳細を忘れます。
でも、別にそれでいいのです。ノートに書き出せば、どれだけでも案を出すことができるし、同じところをグルグルまわることを避けられます。
「覚えていなければ!」と思っている状態は、作業台に書類が山積みになり、不要な文房具が散乱しているような状態で、ライトも必要なところに当たらない…といった具合。
考えるという本質的な作業が全然進みませんから、頭の中の作業台はガラーンとしているほうがいいわけです。
ただ、正直なところ。
私は、もっと大きな紙の上で考え事をしたいんです。

A4ノートは、壁一面のホワイトボード。
そんなときに活躍するのが2冊目。A4サイズの方眼ノートです。見開きにすればA3サイズになります。
これは職員室の机上に待機させる、「大きく考えるとき」用のノートです。壁一面に貼り付けたホワイトボードのような用途ですね。
会議資料やレポートを作成するとか、長期にかかる仕事のアイディア出しをする場合に使用します。ガリレオの湯川先生よろしくどんどん書きます。
アイディアを真ん中から枝分かれさせてマインドマップをつくったり、情報を書いた付箋をペタペタと貼ったりはがしたりして移動させながら考えるんですね。
ですから、このノートは見返してもぐちゃぐちゃです。自由帳的なものですが、wordに打ち込む前に頭が整頓されるので、打ち込みの迷いが少なくなります。
情報や論理展開が整理されていない状態で「とにかく書けば何とかなる」というやり方でいると、「書いては消し」の繰り返しになったり、後半に差し掛かるところで話が破綻していることに気づいたりして修正が難しくなり、納得感のない仕上がりになってしまいますよね。
教員としての軸づくりにもノートは使える。
何をやるにしても、先にノートで思考を整えたほうがいいと思っています。
ノートは、授業準備や資料づくりだけでなく、先生自身の指導方針を熟考するのにも活躍してくれます。
生徒とのやりとりで力不足を感じ、ひとり反省会で落ち込んだときや、学校・学年の方針に違和感を覚えたりしたときに、ノートに考えたこと・感じたことを書き出しておくことをおすすめします。
あなたの考えたことが少しずつ熟成し、あなたの色がしっかり出た指導や提案になっていくはずです。
>>>前回の記事