先生の悩み、抜け出す鍵は「視点」にあった。
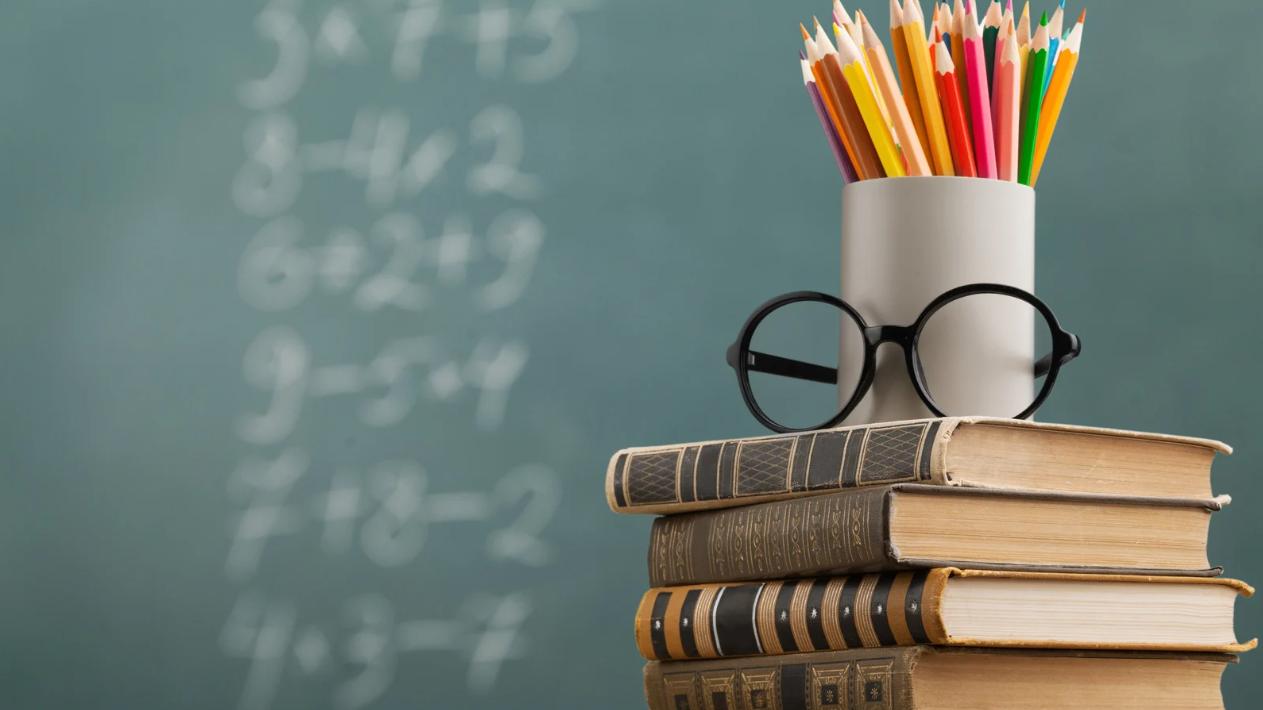
教員専門ライフコーチ蒼井櫻子です。
教員をしていると、生徒・保護者、同僚・上司との関係について悩んだり、考え込んだりしますよね。
なかなか答えが出ないとか、同じところをグルグルめぐって先に進まない感覚に陥ることも多いと思います。
そんなときにようやく辿り着いた答えがあったとしても、何となく疑ってしまって、また考え始めるということがありませんか?
この悶々とする状態を、いわゆる“悩む”というんでしょうね。元々は、論理的な答えを探すために“考え”はじめたのに。
今回は、考えが行き詰まったときに抜け出すアイディアをひとつ紹介します。
この記事を…
視点を動かす前にやること。
コーチングセッションでは、コーチとクライアントが協力することで、一人で考えるのとは違うアイディアを見つけたり、元々出した答えの後押しをしたりします。
そのときに“視点を変える、移動する”という方法をとることができます。
まずは、時間を動かしてみる。
過去の自分、未来の自分からだと、この課題はどう映るだろうか?何と声をかけるだろうか?と考えます。
そして、立場や場所を動かしてみる。
向き合っている相手、尊敬する人、いつもそばにいる人は、この課題をどう見ているか?
あるいは、雲の上から現状を見てみるとどう感じるか?
いつもと違う視点から捉えなおすことで、「なんだ!そんなことか」と問題視する必要がなくなったり、絡み合った紐や鎖がサラッとほどける感覚になったりして、これからできそうなことが見つかることがあります。
ただ、視点を動かす前に大事になってくるのが、“自分自身が現状をどう捉えているか”という部分をしっかり自覚するということなんです。
例えば、自分が今求めているのは解決なのか?解消なのか?という点に注目することができます。
解決とは、問題のある事柄をうまく処理すること。穴の開いた道路を修繕するように、障害になるものを取り除いて整備していく感じでしょうか。
解消とは、今までの状態や関係、約束などが消えてなくなること。起きている事実はすぐに変わらなくても、それによる影響や心理的負担が軽くなることかと思います。
雨天に外出するのが嫌いだった人が、おしゃれな長靴を手に入れたことで雨のお出かけがストレスでなくなる…という感じかもしれません。
(参考『明鏡国語辞典』『デジタル大辞泉』)
果たして、自分が求めているのはどちらなのか?と問い直すことができるわけです。

いつの間にか本質からズレた悩みになる。
もう少し具体的にしてみましょう。
学級経営や授業運営で、それなりの頻度で起こる「クラスに指示が通らない」という事案でお話してみます。
朝礼やHRで話を聴かない
指示したことを生徒がしない
何か起こったときに自分の耳に入らず、他の教員から聞かされる
無力感や無能感といった、大きくて重たい波に飲み込まれる感覚です。
「あぁ、自分はできないやつなんだ」
自分自身を心の中で指差し笑い、目の前にいる何十人という生徒も自分を嘲り笑っているように見える。
覚えのある先生、いらっしゃるのではないでしょうか。
それでも毎日HRや授業はあるわけで、日々思考停止と自己否定が繰り返されるなか、どうしたらいいんだろうと考えますよね。
(あくまで「問題」として感じ始めた初期段階で、の話ですが)
頭の中でどんな考えが巡っているのか、に集中してみてください。ちょっと面白いことがわかります。
ケース1 他者からの評価
最も恐れているのは、他の先生から「アイツ仕事できないよね」と思われて恥ずかしいと感じること。
だから、現状から一刻も早く抜け出すために即効性のある解決策を考え続けている。
自分を大きく強く見せようとして、どんな台詞を言えばいいのか、どう振舞えばいいのか、と形が気になってしまう。
以上の点に気づくと、他人の目を気にして生活している自分の存在や、生徒に言うことを聞かせるという、大人視点での形式上の解決策を考えていることがわかります。
お互いの行き違いやわだかまり、クラスの中に隠れている本質的な問題にアプローチするという発想はありません。
ゆえに、ネガティブな空気感は解消されないし、本当に大事なことは解決もされません。
ケース2 先々の不都合に意識が向く
これから学校祭があって、生徒会に提出しなきゃいけない書類もいろいろあるのに、生徒が言うことを聴かないのでは準備が滞ってしまう。
生徒会に迷惑かけられないし、当日に完成しないのではないか。
先々に起こる事務的な問題が気になって、一人で企画書や予算の提出、買い出し、組み立てなどなど、何とかしようと考え始めている状態です。
クラスの問題そのものから意識が離れていますよね。
でも、精神的な余裕がないとこういう考えにいたることは普通に起こります。
実際は、期限に間に合わずに生徒会の許認可が下りないことにも意味があり、そのなかで取り組んだ結果、学校祭の真っ最中に完成することだっておかしくありません。
自分が何かの理由で、それを認めないだけの話なのです。
ここでは2つだけ挙げてみましたが、あなた自身が一番気にしていることは何か?と考えてみると、いつの間にか本質からズレていたことに気づけるんですね。
一旦、冷静になることができますし、自身の認識を把握したうえで先輩や上司に相談すると、よりアドバイスをもらいやすいはずです。視点を切り替えやすくなるのは、こういうときなんですね。
生徒から見たらどう写っているか?
室長・級長から見たら?
いつもクラスを俯瞰しているあの子なら?
隣のクラスの先生から見たら?
学年主任から見たらどうか?
1年単位で考えるとどうか?
教員のキャリアで見ると?
他者の視点を借りるつもりで、未来の自分の視点を借りるつもりで考え直すと、客観視しやすくなるはずです。
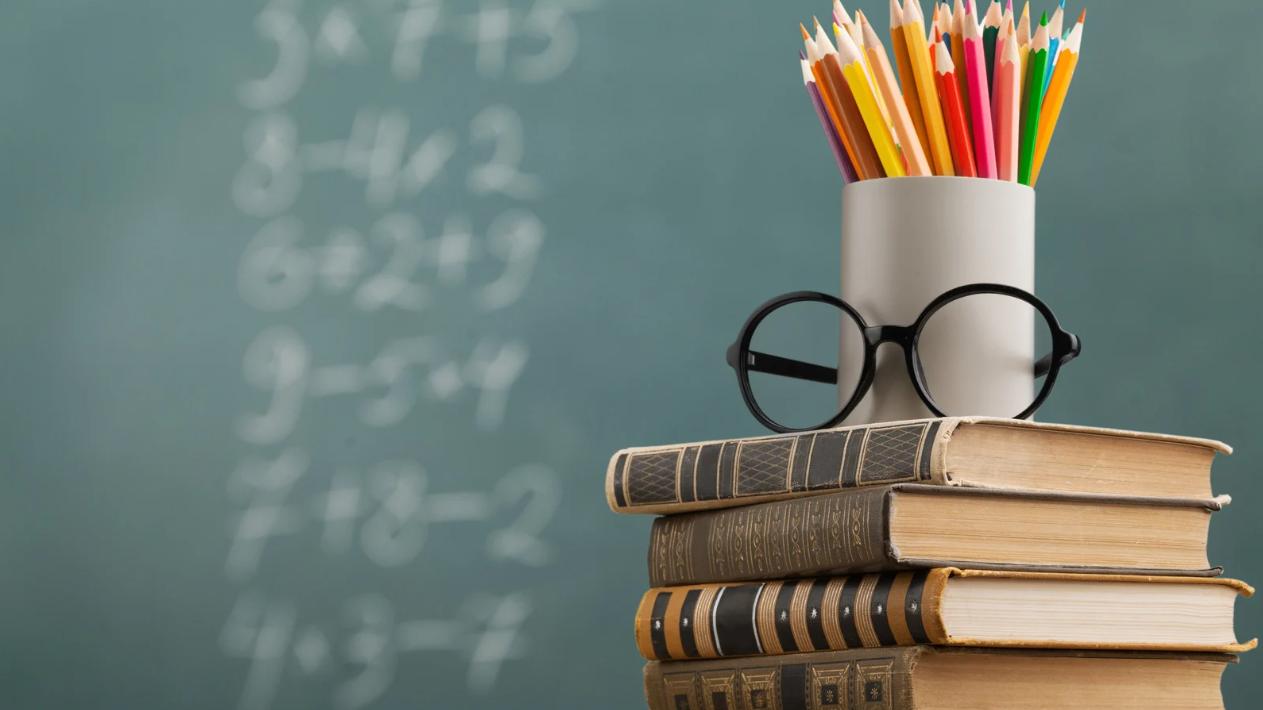
「先生ってうちらのこと、嫌いなんでしょ?」の行き違い。
実際に、他者から見ると全然違っていたということがありました。
生徒に話が通じないのはどうしてだろう?と悩んでいた時が何回かありました。
理解が食い違うとき、顕著に反発を感じたとき「どうしてそうなるの?」と焦って固まってしまっていたんですね。
結局、のちに生徒から聞いたのは2パターンでした。
「先生の使う言葉が難しくて、何言ってるかわからない」
「うちらが何か言うと、嫌な顔するじゃん。うちらのこと嫌いなんでしょ」
私の言葉遣いが難しい、という声には学力低下の危機感を覚えましたが、「ここまでわかった?」とか「何がわからなかった?」と聞き返すことで、お互いに困り感はなくなっていきました。
“嫌な顔”については、私の感情が顔に出やすいという短所が足を引っ張ったなと感じますし、そもそも生徒たちにオープンになれていなかったんだろうとも考えました。
何より、生徒たちの表情から違和感を見出したら「どうした?」「何が気になった?」と焦らず普通に別の球を投げればよかったわけです。
他のクラスでは、こんな話も生徒たちから聴きました。
先生の言うこととやることがズレていて、信用できない。
いつも声が大きいから、何が大事なのかわからない。
本人たちは、言うことを聞いていないと思っていない。
主張の強いクラスメイトに引っ張られている。
起きていることとしては、教員の指示がうたわらない、ということで同じであっても、表に出てきていない部分ではまるで食い違っているなんてことが、自然に起こります。
難しいのは、すぐに気づけないということなんですが、教員は全知全能ではありませんから、できることをやるだけなんですよね。

正面から食らっても大丈夫。
何だか判然としないモヤモヤした表情を生徒がみせたとき、直接やり取りして聞いてみるというシンプルな方法が少しずつ効果を発揮することがあります。
生徒とクラスがどうあるべきか?と議論できることも増えました。
もちろん、私にも「先生は舐められてるよ」とか「先生のことが嫌い」とストレートに言われた経験がありますし、諦めたくなった生徒もいます。
肝心なのは、そういうことが起こって正面から食らったあとの回復や対応、精神的なタフさなのかもしれません。
だからこそ、向き合っている問題について自分が何をどうしようと考えているのか?という思考自体に目を向けることができると、ベターな道を探りやすくなります。
今回のお話は、プライベートでも応用することができますので、試してみてくださいね。